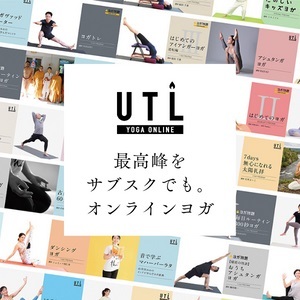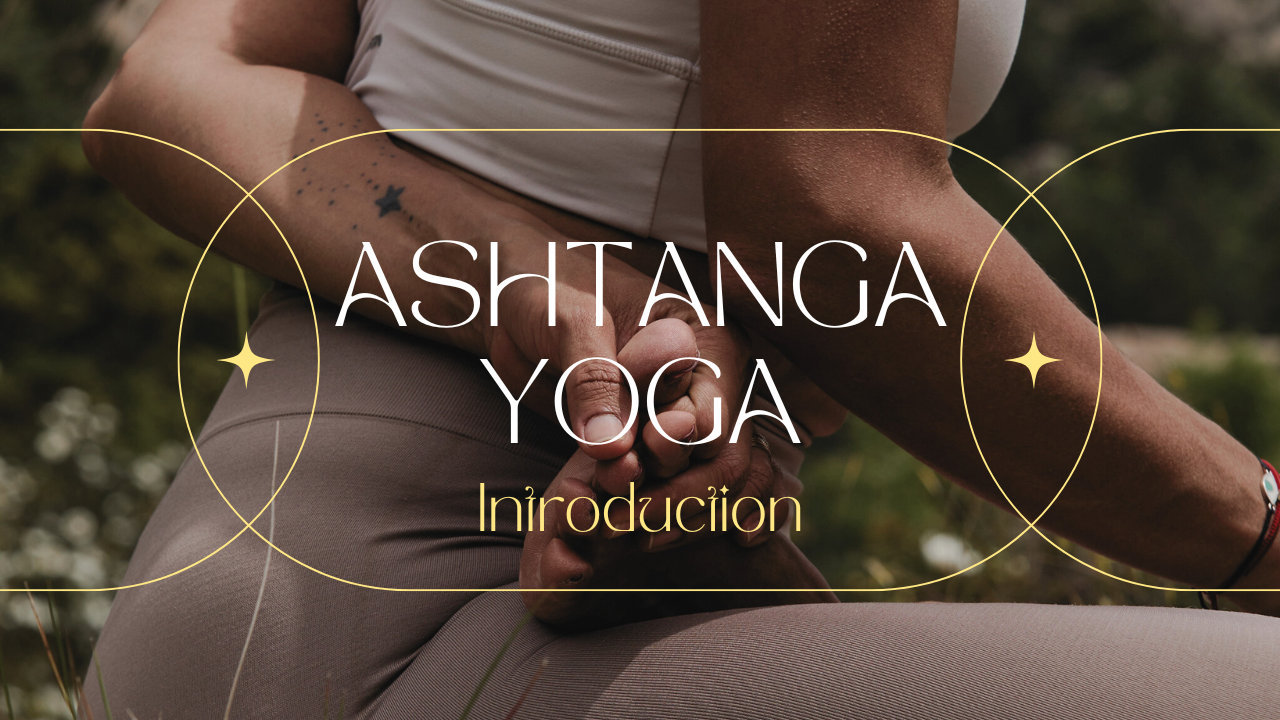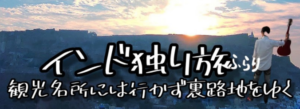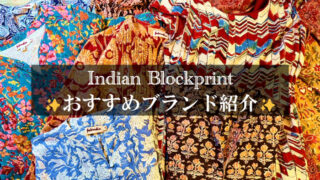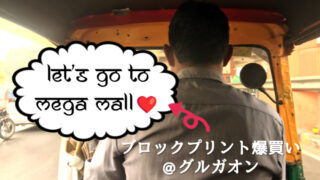Namasteです!Ashaです。
昨年に突然の宣言をしましたが、24年春からRYT200の勉強とともに本格的にヨガを始めました!!
それまでのヨガ経験は(インドに住んでいたものの…)ぎゅっと凝縮して3ヶ月くらいでした。
幸い会社にフレックス制度が入ったので、早速仕事を早上がりしてRYT200を勉強していたスクールの夜クラスに定期的に通い始めました。
好きなスタイルのクラスに通っていたのですが、ヨガというものを掘り下げる中で魅了されたのが「アシュタンガヨガ」という流派でした。
またまた幸いにも同じスクールで夜のアシュタンガヨガのクラスもあり通っていたのですが
アシュタンガヨガについて調べ、ワークショップに参加する度に「マイソールクラス」という化け物システム(失礼)の存在が濃くなり、どんどん興味が湧いてきました。(何故化け物なのかは後ほど…)
そして今、平日仕事前の朝にマイソールクラスで師のもとアシュタンガヨガを練習しています。
ヨガでは、体系化されたハタヨガをベースに様々な流派があり、その中でも「アシュタンガヨガ」は、一言でいうとダイナミックで力強いフローやアーサナ(ポーズ)が特徴的な流派のひとつです。
今回はアシュタンガヨガの基本情報として、歴史・特徴と目的・システムと練習法について、いちプラクティショナーが解説します!
これからヨガを始める方や、アシュタンガヨガに興味を持っていただいている方へ参考になりますように✨
アシュタンガヨガの歴史
アシュタンガヨガは5000年の歴史があるインド発祥のハタヨガの中でも現代ヨガにあたる一流派です。
19世紀に運動的要素を取り入れた流れるように連続するポーズで動く「ヴィンヤサ」システムが考案された後に
青少年の健康の為に運動量高く身体のパーツを順番に鍛えるポーズの流れで、実践を通してヨガにおける生活行動規範も実践できる「アシュタンガヨガ」がひとつの流派として確立されました。
「パワーヨガ」として欧米にエクササイズ的な立ち位置で広まり、ヨガというものが広く認知されていったことに貢献したのもアシュタンガヨガと言われています。
アシュタンガヨガは、20世紀のインドのヨガマスターであるシュリ・T・クリシュナマチャリア氏(Sri T. Krishnamacharya)と、その弟子であるシュリ・K・パタビ・ジョイス氏(Sri K. Pattabhi Jois)によって広められました。パタビ・ジョイス氏は、クリシュナマチャリア氏の教えを基に「アシュタンガヴィンヤサヨガ」として体系化し、世界に広めました。
現在では、その最高指導者(グルジ)のパタビ・ジョイス氏(1915-2009)やその孫のシャラート・ジョイス氏(1971-2024)から教わった多くのヨガティーチャーやその弟子の皆さんが世界各地でアシュタンガヨガを教え、多くのヨガ実践者に影響を与えています。
わたしもグルジから無数に繋がる枝葉のひとりの練習生として実践しています。
アシュタンガヨガの生まれた場所(総本山)はインドの中でも南部の大都市ベンガルールに近い「マイソール」というエリア。実はすべてのヨガはリシケシュという訳では無いと、アシュタンガヨガを通して初めて知りました。
アシュタンガヨガの特徴と効果
アシュタンガヨガの最大の特徴は、決められたシークエンス(順番)でアーサナ(ポーズ)を実践し、呼吸と動きを連動させながら流れるように行う「ヴィンヤサスタイル」です。
「動く瞑想」ともいわれるアシュタンガヨガの本質がここに詰まっています。
1. 決められたシークエンス
アシュタンガヨガには、プライマリーシリーズ(初級)、インターミディエイトシリーズ(中級)、アドバンストシリーズ(上級)といった段階的ごとのシークエンスが設定されています。
それぞれのシリーズで特定のアーサナとその順番が決められており、基本的にその順番を守って練習していきます。
どのシークエンスを練習するにしても、太陽礼拝(A&B)から始まります。
練習するその時の自分自身の体調・怪我やペースなどに応じて、太陽礼拝のみだったり
「今日は立位(スタンディングアーサナ)とフィニッシングだけ」とパートを分解して練習することもあります。
継続して練習することが大切なので、個々人が続けられるやり方で実践することも奨励されています。
また、アーサナが決まっているからといって、そのアーサナのお手本の形が出来ないといけない訳では全くありません。
それぞれのアーサナに緩和ポーズがあり、例えば膝が痛くて蓮華座(パドマーサナ)が出来ない場合は胡坐(スカーサナ)で行うし、前屈で無理をして足を掴むことも、両手を結ぶときに手首を無理に掴む必要もありません。
わたしもしばらく膝の曲げ伸ばしをする筋肉を痛めてしまい、蓮華座が出来なくなり勝手に落ち込みました…が、お手本のポーズが出来なくても練習の本意(集中)には影響が無いことを忘れずに、そしてその日痛い動きはしない!を念頭に練習を継続しています。
2. トリスターナ(Tristhana):「3つの柱」
アシュタンガヨガでは、以下の3つの要素が重要視されます。
- ウジャイ呼吸(Ujjayi Pranayama):勝利の呼吸とも言われる。喉を締めて行う深く安定した鼻呼吸によって、身体を内側から活性化し、集中力を高めます。
- バンダ(Bandha):バンダはエネルギーロックとも言われますが、アーサナごとに特にムーラバンダ(骨盤底筋)、ウディヤナバンダ(腹部の引き締め)、ジャーランダラバンダ(喉の圧迫)を意識し、エネルギーをコントロールします。
- ドリシュティ(Drishti):身体の部位など特定の視点に視線を固定し、アーサナ実践中の集中力と内面への意識を高めます。
この3つは毎回の練習で一秒一秒いつも意識しています。
1つ目のウジャイ呼吸は初めて行うときは練習も必要だったし、やりすぎると常に呼吸がウジャイっぽくなってしまいなんか喉が苦しいなんてことも正直ありました。
ですが、慣れてくると、毎回一番最初の太陽礼拝を始める時の深く長いウジャイ呼吸が練習開始のスイッチになり、そして苦手なアーサナに取り組むときも呼吸を意識して、呼吸と一緒に動き、身体の感覚や力の入れ方、抜き方に集中します。
そして、2つ目のバンダの中でも一番大事なのがムーラバンダ(骨盤底筋)。
初めは骨盤底筋ってどこ?と謎でしたが、感じるとすると尿を我慢するときに締まるインナーマッスルなのだそう。
そしてロックするにはその筋肉を引き上げ、下腹部をそこに向かって近づけるイメージで下腹部をへこませる…など色々教わってきたものの、アーサナを練習しながらまだまだ探り中です。
(エネルギーが抜けちゃっているかもしれないと感じることも多々あります。汗)
そして3つ目のドリシュティは先生に常に注意されるポイントだったりします。アーサナごとに鼻先、眉間、手、おへそなどと決まっています。(最初は覚えるのが大変!)
練習し初めの頃は、周りの大先輩方のものすごい超人アーサナの美しさが気になって自分も練習しているのにチラチラ見てしまったり、見られているかもしれないと気になって逆に見返してしまったり、シークエンスを忘れて「はて?」と目線が空中を泳いだり…。
ですが、練習を重ねて全てのアーサナのドリシュティを覚え、意識して呼吸と共に合わせて動くことで、格段に集中力が高まって練習の質も良くなることをだんだん実感しています。
この集中がものすごく大事で、自分に集中することで練習している場所で周りを(良い意味で)気にしなくなるので、超人的で美しいダイナミックなアーサナへの憧れや、他人に見られているかもしれないという思い込みの恐怖や恥を手放すことができるようになりました。(アパリグラハ👋)
また、一瞬一瞬の自分の身体の動きや感覚を敏感に感じることになるので完全なる「観察者」になります。ということは、こころや自我に混同しない、インド哲学でいう「アートマン(真我・意識の根源)」を探る一助になるのではないかなと個人的に感じています。
またインドヨガ哲学のお話はどこかで…✨
3. ダイナミックなフローとデトックス効果
最大の特徴のひとつである呼吸と動作を連動させたダイナミックなフローは、身体をエネルギーで満たして内側から温め、汗をかくことでデトックス効果ももたらします。
また、心肺機能を向上させるだけでなく、柔軟性と筋力の両方をバランスよく鍛えることができます。
フローの中には、始まりがそもそも先述の通り青少年向けに作られたシークエンスということもあり、ジャンプやでんぐり返りなど楽しい一面もあったりします。
とはいえ、そのダイナミックさは魅力であると同時に、集中力が欠如した練習をすると怪我にも繋がりかねないものです。バランス系で転んだり、逆立ちから落ちたり、着地で強打してしまったり…。
どのヨガ流派でも同じことが言えると思いますが、やはり「集中」が鍵になるのです。
4. 練習スタイル:マイソールスタイルとレッドクラス
アシュタンガヨガには2種類の練習スタイル:マイソールスタイルとレッドクラスがあります。
このマイソールスタイルこそが、わたしが「化け物」と思った理由のひとつです。笑
マイソールスタイル(Mysore Style)
マイソールスタイルは、アシュタンガヨガの伝統的な練習方法で、指導者のもと個々のレベルやペースに合わせてシークエンスを進めていく自主練スタイルです。
通常、クラスとして練習する時間は早朝6時頃〜午前中の2時間程度で、生徒は自分のペースでアーサナを行い、必要に応じて個別に指導が入ります。
初めてマイソールクラスに参加する場合、太陽礼拝やスタンディング(立位)などの基本的なシークエンスからスタートし、習熟度に応じて徐々にアーサナを増やしていきます。
自分のペースでの練習を重視しながらも、正しいアライメントや呼吸法を丁寧に身につけていき、練習を重ねることで深い集中状態で進んでいくことも可能になります。
理想的には連続した日数で固定した師のマイソールクラスに通います。師匠(インストラクター)を固定することで、自分の動きの癖や身体の特徴や成長を掴んで指導をしてもらえるようにもなります。
また、決められた順番で毎日同じような時間に同じ場所で練習を行うため、継続することで身体の柔軟性や筋力と体を使う感覚が向上するのをしっかりと実感でき、動きながらの瞑想的な要素も強くなります。
わたしも昨年の夏からこのマイソールクラス(平日5日/週)に通い始めました。
おかげで平日朝は5:30に起きて7:00くらいから練習を開始して、10:00までには出社するルーティーンになりました。
完全夜型一筋31年だったわたしにとって、空前絶後の~超絶早起き~!(サンシャイン☆)なだけでなく、朝っぱらから身体を大きく動かしてその後仕事もするなんて「化け物システム」だと感じていました。(ごめんなさい)
そして周りの大先輩達はこの早朝練習を10年くらい続けている。その自然さに尊敬しか無いし、自分もいつか生活の一部として当たり前のものとして継続出来るよう日々修行です。
眠くて行くのがしんどい日もまだまだ全然あります…
レッドクラス(Led Class)
レッドは赤(Red)ではなく導かれるのレッド(Led)である通り、インストラクターがカウントを取りながらクラス全体のフローをリードするスタイルです。
クラスの時間はシークエンスレベルやカウントの長さにもよりますが、1時間半から2時間程度で、太陽礼拝からフィニッシングまで、決められたシークエンスを全員で一斉に行います。
インストラクターのガイドに従うため、初心者でも流れを把握しやすく、リズムよく動けるメリットがあります。ただし、カウントに合わせるため、自分のペースで進めるマイソールクラスとは異なり各アーサナのホールド時間が長く統一され大変なこともあるかもしれません。(特にバランスアーサナなど…)
レッドクラスは、シークエンスの順番や正しいヴィンヤサ、そして呼吸と連動して動くことを再確認し、グループで実践することによるエネルギーを感じながら練習を深めることに適しています。
ワークショップで聞いたお話によると、アシュタンガヨガが広まった初期にはマイソールスタイルしか行われておらず、師匠から弟子へアーサナを指導し伝える形式(パランパラ)のみだったそうです。
しばらくしてアシュタンガヨガ実践者が世界中で爆発的に増え、海外でワークショップを行ったグルジが100人程の練習生を目の前にして一人一人を見られないことからレッドクラスというスタイルが生まれたんだとか。
わたしも最初に参加したアシュタンガヨガのクラスはハーフプライマリーのレッドクラスでした。そこから、よりアーサナひとつずつを学び、日常的に練習したいと感じたことでマイソールクラスに通う決心をしました。
初めてレッドクラスに参加すると、難しいポーズが沢山でびっくりするかもしれないですが、アシュタンガヨガのエネルギーや基本的なエッセンスを感じる良い機会になると思います!
グループレッスンでは焦るかもしれないですが、今現在の自分の身体で無理に感じるアーサナに執着する必要も、恥ずかしさを感じる必要もありません!Just give it a try!
アシュタンガヨガのシステム
アシュタンガヨガは、身体のパーツを順番に強化していく体系的に組み立てられたシステムとシークエンスに基づいており、以下のシリーズ(レベル)があります。
- プライマリーシリーズ(Yoga Chikitsa:ヨガセラピー)
身体を浄化し、基礎を築くシステム。
※途中までのハーフプライマリーもあります。 - インターミディエイトシリーズ(Nadi Shodhana:ナーディ浄化)
エネルギーの通り道(ナーディ)を開き、心身のバランスを整えるシステム。 - アドバンストシリーズ(Sthira Bhaga:力強さと優雅さ)
高度なアーサナを通じて、より深い集中力と高い身体能力を養うシステム。(4段階)
プライマリーを1stとして、インターミディエイトが2nd、アドバンストシリーズが3rd~6th(またはアドバンストA~D)と呼ばれます。
昨年のワークショップ時点では、グルジ以外のプラクティショナーで一番進んでいるのは4thが終わったあたり、だそうです。(もはや6thには何があるんだろう)
また、余談ですが、この6段階のシステムに加えて7thがあると言われており、7thは結婚して家庭を持つことだそうです。(アーサナを離れたカルマヨガの世界)
ヨガは社会でも苦しまずに自由に生きていくことがゴール。そんな原理に基づき、自分の人間社会を広げる行為=家庭を持つこともアーサナのシリーズに加えて推奨されているんだとか。(※諸説あり)
それぞれのシリーズに含まれるアーサナですが、プライマリー(=初等)といいながらハーフプライマリーシリーズですら強い筋力や柔軟性が必要なアーサナで構成されていると感じます。
アシュタンガヨガをマイソールクラスで実践し始めて約8ヵ月のわたしですが、先生や先輩方に励ましと共に鍛えてもらったおかげで、現在はハーフプライマリー+αを練習中です。
目指せプライマリーシリーズコンプリート!(目標は持つけど、焦らず気長に)
最初に覚えたいハーフプライマリーシリーズのシークエンスはこちら(「フレアプラス」様)のアーサナマップを参考にしてみてください!
まとめ
「アーサナの練習」のみの概念を超えたアシュタンガヨガは伝統的な実践法でありながら、呼吸・バンダ・目線を重視しながら集中と共にアーサナを繋いで動く「ヴィンヤサ」スタイルや「レベルごとに決まったシークエンス」、そして一般的には自主練スタイルか一斉カウントスタイルで練習するという独特な特徴を持っています。
現代のヨガ実践者にも、八肢則を含むヨガの重要なエッセンスを体現できることから多くの恩恵をもたらしています。
きついストイックなイメージのあるアシュタンガヨガですが(私も始める前はそうでした)、アシュタンガヨガは「誰もが実践できるヨガ」とインド総本山のグルジは言います。年齢も、性別も、身体や怪我も、関係無い。決まったシークエンスでも緩和ポーズがあるし、自分の状況に合わせた進み方をします。
そして、アシュタンガヨガを唯一実践できないのは(練習を完全に放棄する)怠け者だけ、と続けます。
もちろんヨガにはアシュタンガヨガ以外にも様々な流派や、さらには先生一人一人ごとのオリジナルなレッスンを体験できる機会がたくさんあります。
どんなヨガの経験や練習をしていても、5000年以上続くインドの知恵を生活に取り入れ、日々を生きる活力や支えとなる貴重なものです。
そんな中でアシュタンガヨガに興味を持った時に、スタジオやオンラインクラスに踏み出す初めの一歩の切欠になれればとても嬉しく思います!
皆さまのyoga journeyが充実したものとなりますように🙏
👇私のRYT200母校、アンダーザライト(UTL)ヨガスクールでもアシュタンガヨガのスタジオ/オンラインクラスがあります。
経験豊富な講師陣から学べる機会をぜひチェックしてみてください!